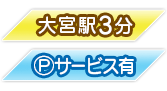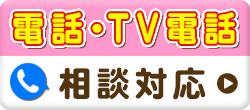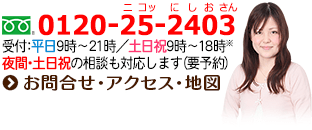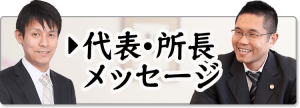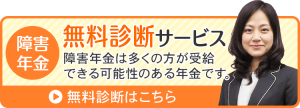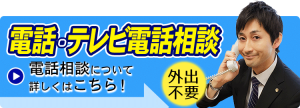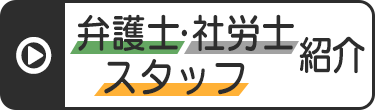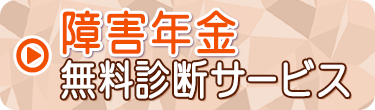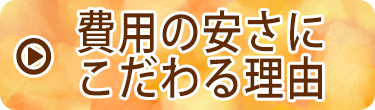線維筋痛症で障害年金を請求する場合のポイント
1 線維筋痛症で障害年金を申請するにあたって
線維筋痛症も障害年金の認定対象となりますが、日本年金機構としても「障害認定困難な疾患」の1つとしている傷病でもあります。
線維筋痛症は、「原因不明であらゆる検査でもほとんど異常が認められない」という特徴があります。
線維筋痛症の上記のような特徴を踏まえ、以下で請求時のポイント等をご説明いたします。
2 初診日の特定について
障害年金の受給申請においては、初診日(申請傷病について初めて医療機関を受診した日)の特定が重要となります。
線維筋痛症は、四肢の痛み等の症状から病院に行って検査をしても、異常が認められない可能性があります。
そのため、実は線維筋痛症の症状に起因する通院だったにもかかわらず、異常が見つからず、線維筋痛症と診断されない場合も十分あり得ます。
そうなると、検査の異常もない通院が初診日となるのか、どうやって判断するのか、といった問題や、「初診日が分からないから」という理由で障害年金を受け取ることができないといった問題が生じてしまいます。
この点に関して、確定診断された日が初診日になる場合があるほか、厚生労働省から事務連絡が出されており、発症直後に確定診断が行われなかった理由に関する申立て等を踏まえて、請求者が申し立てた日に線維筋痛症の症状で診察を受けたと認められる等の場合は、その日を初診日と認める取扱いも行われています。
初診日は保険料納付要件の判断基準ともなる日となっていますが、過去の記録などを十分整理、保管しておくことがポイントといえます。
3 等級判断について
⑴ 申請書類
線維筋痛症については、通常肢体の障害用の診断書を用いて申請を行います。
加えて、線維筋痛症の診断書作成にあたり、日本年金機構のサイトにて、「線維筋痛症の障害状態について診断書を作成されるお医者様へ」という線維筋痛症用の書面を掲載しており、特に「重症度分類試案」に基づくステージの記載を求めています。
参考リンク:日本年金機構・化学物質過敏症、線維筋痛症、脳脊髄液漏出症、慢性疲労症候群の診断書の記載例や認定事例等
また、診断書記載例のほか、ステージⅤを1級、ステージⅢを2級、ステージⅡを3級とした認定事例も掲載しています。
審査自体は他の診断書の記載、病歴等も含めた判断となるため、ステージいくつであれば何級と明言できるわけではありませんが、受給の可否等について参考になる資料といえます。
⑵ ステージの評価
ステージの評価は医師の判断によることになりますが、各ステージは、「日常生活がやや困難」「自力での生活は困難」等という評価となっています。
そのため、日常生活上線維筋痛症がどのように影響を及ぼしているかをしっかり伝えておくことが申請にあたっては大切になってきます。
その他、「紐を結ぶ」「ズボンの着脱」等の日常生活動作についても、どの程度の不自由が生じているのか、しっかり状況を伝えて診断書に正確に反映してもらうことも重要になってくるといえます。